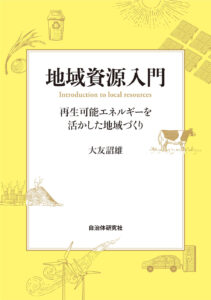リニア建設にともなう大規関開発の論点
東海自治体問題研究所
梅原 浩次郎(当研究所事務局長)
リニア中央新幹線(以下、「リニア」と略称)は、2011年5月全国新幹線鉄道整備法に基づき、営業主体及び建設主体にJR東海が指名されました。その後、リニアは2014年10月工事実施計画(品川・名古屋間)の認可を受け、建設段階に入りました。いま、名古屋駅周辺地域では大規模なビル建設が進行しています。そこで、大規模開発はなぜ起きているのか、大規模開発の重大な論点、の順に考察をすすめることにします。なお、本稿は、第41回東海自治体学校分科会(2015年5月17日、愛知学院大学)などの報告をもとに、修正加筆したものです。
1、大規模開発はなぜ起きているのか
(1)名駅周辺で進む開発ラッシュの背景
「都市間競争」を奨励
この問題の背景には、特に2000年代以降の日本企業の中国・東南アジア等への工場移転と現地生産化、その一方で国内市場の停滞・収縮があります。2008年のリーマンショックや2011年の大震災は海外生産を加速化させ、2013年の第2次安倍内閣による異次元金融緩和は国内の購買力をいっそう縮小させました。国土形成計画(2008年)は、グローバル化や人口減少に対応する国土計画として、東アジア市場をにらんだ企業の新しい発展戦略、観光立国、交通・情報通信ネットワークの形成をあげています。また、「国土のグランドデザイン2050」(2014年)は、リニア整備で、東京圏の国際的機能、名古屋圏の先端ものづくり、大阪圏の文化、歴史、商業、を一体化させ、世界から人・モノ・カネ・情報を受け入れることを強調し、「日本の存在感を維持していくためにも、大都市の国際競争力の強化が課題」であるとしています。国土計画そのものが、大都市による交通基盤整備・観光事業への参入に力点をおいた内容になっています。バブル崩壊後の20数年間に国内生産の縮小と雇用破壊を進め、そうして生まれた困難を打開するために都市間競争を奨励して地方の都市と資金をも動員しようとするところに、問題の本質が潜んでいるとみることができます。以下、大規模開発の動向を見てみましょう。
大規模開発計画の新聞報道
2015年3月、東京と金沢を結ぶ北陸新幹線が開業しました。この前後を通して、「北陸・首都圏交流の旅」(日経、3月14日)や、交通関連・観光事業にかかわる大規模開発計画がマス・メディアで一斉に報じられました。例えば、「国内で都市の競争力を取り戻すための再開発が広がってきた。三井不動産と東京建物は2017年度からの東京駅八重洲口の再開発に6千億円超を投じる。国の規制緩和策の国家戦略特区を使い地上約50階の超高層ビルを2棟建てる。アジアの都市間競争が激しくなるなかインフラ機能を高めてグローバル企業を誘致する」(日経、2015年3月5日)というのである。国家戦略特区というのは、第2次安倍内閣の成長戦略の柱であり、総理大臣主導で事業が決定され、長年にわたって築きあげられてきた各種規制の緩和を実施し、国内外の投資や人材を呼び込んで経済活性化を目指す制度といわれています。
リニアと交通関連事業の再開発の流れに、名鉄再開発計画なども位置づけることができます。「2027年のリニア中央新幹線の開業に合わせて、名古屋駅前で名古屋鉄道などが進めている再開発計画に『日本生命笹島ビル』(地上17階、地下1階建て)が参加し、一体となって開発する方針を固めた」(中日、2015年3月15日)と報道されています。「計画地の南隣にある笹島ビルが加わることで、対象エリアは名鉄百貨店本館から南北400メートルに拡大。敷地面積も28,000平方メートルに広がり、中部地方で最大の再開発プロジェクトになる。名鉄が23日(注:2015年3月)に発表する中期経営計画に盛り込む」とのことです。名鉄は、自前の資金を活用することは言うまでもありませんが、国や地方自治体の制度を最大限活用し、この事業に臨もうとしていることはいうまでもありません。
名古屋市・愛知県の計画一ストロー現象を懸念するが一
「名古屋市総合計画2018」(2015年)は、リニア開業に伴う東京一大阪間の大交流圏形成を期待しつつ、一方で人口や経済活動が吸い取られるストロー現象の懸念を表明しています。しかし、その検証には触れていません。国際的な都市間競争が激化するなかで、リニア(2027年)、東京オリンピック(2020年)を圏域の成長につなげる、そのためにリニア開業を見据えた名駅周辺のまちづくりを行い、名駅周辺・栄を2核1体とする都心部形成を行うというの基調として描かれています。
愛知県『あいちビジョン2020』(2014年)でも、産業活動や観光などへの期待の一方で、支店・営業所の撤退や、消費・文化活動などが首都圏に流出するストロー現象を懸念しています。オリンピック開催により東京へ一極集中が加速することを想定し、県内都市でも名古屋依存が高まり各都市の自律性や活力が低下することを懸念しています。残念ながら、中小企業や地域住民に対する抜本的な地域戦略を持つには至っていないと見ることができます。名古屋圏域で製造業が一定の役割を果たすとしても、東京へのサービス・金融業の集約化が進むことは確かです。何よりも、人、モノを呼び込む外来型発想だけでは地元地域で活動する企業の持続性はいうまでもなく、地域の未来は見えてきません。
(2)開発の根拠法(都市再生特別措置法)とその不当性
規制緩和と優遇措置で外国会社などを援助、開発の根拠法とされる都市再生特別措置法は、小泉内閣のもとで2002年2月に制定されました。2000年代初頭に海外生産が急増するなかで、国内産業に刺激をあたえるためでした。同法での「都市再生」とは、「都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上」(第1条「目的」)を図るとされています。「都市の国際競争力の強化」については、「都市で、外国会社などによる国際的活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業を通じて、活動拠点形成に資するよう、都市機能の高度化、及び都市の居住環境を向上させる」(定義第2条第4項)と記されています。つまり、法の対象は都市開発事業であり、都市に企業のヒト・モノ・カネを呼び込むために、都市環境を整備し、都市を売り込むためとしています。「外国会社などによる国際的活動」の援助のためであり、一般に地域の中小企業、住民は埒(らち)外に置かれています。
都市再生緊急整備地域は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、政令で指定する全国63地域です。特定都市再生緊急整備地域は、上記地域の内から、特に有効な地域として政令で指定する12地域です(2015年7月24日現在)(国交省HPより)。指定地域では、次の優遇措置が用意されています。①規制緩和による都市計画の特例、②国の金融支援(資金の貸付、社債の取得、債務の保証)、税制支援(所得税、法人税、登録免許税、不動產取得税、固定資產税、都市計画税について軽減等)の措置。③都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域のうち、都市再生特別地区の指定を受ければ、既存の規制の一部を適用除外として許可等によらず建築確認のみで実現が可能となります。
名古屋駅西側が開発のターゲットに
こうして企業活動の自由の保障と企業支援、徹底した規制緩和が行われます。都市計画関連法についていえば、長年にわたる都市建設の蓄積のうえに今日の規制法が成り立っているといえます。名目は何であれ、一気に規制を取り払ってしまうところに、根拠法の不当性が潜んでいるといえます。名古屋市内では「都市再生緊急整備地域」が、名古屋市面積32,643ha(326.43ki)のうち、約570ha(うち「特定」約303ha)です。このうち名駅周辺・伏見・栄地域約401ha(うち「特定」約303ha)、千種·鶴舞地域約24ha、臨海地域約145haです。名古屋市全市の約57分の1の広さが指定され、名古屋市の相貌を激変させる事態が予想されます。なお、第2次安倍内閣の成長戦略の柱としての国家戦略特別区域法(2013年制定)に基づく国家戦略特区について敷衍(ふえん)しておきましょう。産業の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点形成のために区域を指定し、規制緩和、国内外の投資や人材呼び込んで経済活性化をめざすものです。地方創生特区は、国家戦略特区の地方版です。都市再生特別地区は少なくとも都道府県が都市計画の手続を経て決定するのに対し、国家戦略特区は総理大臣を本部長としその意図を貫徹させる開発が目指されています。この点が大きく異なります。
2.大規模開発の重大な論点
(1)大規模開発によって何が起きる
開発の果実はどこに
名古屋市は、「名駅周辺のまちづくり構想」(2014年9月)を決定しています。リニア開業(2027年)を見据えた構想であり、行政と民間が一丸となって実現する構想と位置づけています。目標とする街の姿は、「スーパーターミナル・ナゴヤ」(国際レベルのターミナル駅を有するまち)です。基本方針には、①国際的・広域的な圏域の拠点・顔を目指す、②誰にも使いやすい国際レベルのターミナル駅をつくる、③都心における多彩な魅力をもったまちをつくり、つなぐ、④リニア開業を見すえ、行政と民間が一丸となり構想を実現する、としています。
ここから言えること、その一部を指摘しておきましょう。第1に、名古屋市、愛知県が総合計画で指摘するように東京への一極集中、愛知県内では名駅への一極集中、そして県下都市の名古屋依存と衰退が予想されることです。いわゆる都市の階層化と格差が進み、交通の拠点駅から離れる地方は繁栄から取り残されることになります。第2に、グローバル化、都市間競争は、一般に大手企業の競争力強化に役立ち、大型開発に関与しない企業と市民にはその果実は回ってきません。ましてや、少子高齢社会で、現在国民が抱えている生活困難を解決することとは無縁といえます。第3に、名古屋駅西地区については土地利用計画の現状を指摘し、地権者の及ばないところで土地の高度利用が目論まれています。当該地域住民にとっては、高度成長期やバブル経済期に国民が経験した、市場原理優先の地上げの荒波にさらされることが予想されます。
「ビジネス拠点・交流拠点」形成は何をもたらすか
「名駅周辺のまちづくり構想」の基本方針の最初に、「ビジネス拠点・交流拠点に必要な都市機能を強化」することが謳われ、都市再生特別地区等の都市計画制度を活用して民間再開発を進めるとしています。「業務・支援機能」などをあげていますが、果たしてこのまま進めばどんなことになるのでしょうか。都市開発史を振り返ると、オイルショックを経て、名古屋市は名古屋圏の中心都市としての「卸売機能に代表される広域流通拠点都市」を目指してきました。しかし、バブル崩壊以降2000年代に入って、市内の卸売業や小売業の事業所数、従業者数の3分の1が減少し、いまなおその傾向は続いています。2005年の愛知万博開催・中部空港建設を経てからは、「モノづくりの中枢圏域を支える国際ビジネス拠点都市」が目指されました。2008年のリーマンショックや2011年の大震災を経て、企業数はいっそう減少を続け、外資系企業に至っては人口150万人の神戸市と比較してもその半分以下です。「減税で企業を呼び込む」と主張した河村市長の見解は単なる願望に過ぎなかったのではないでしょうか。表1は、この地域の卸業・小売業が全体として落ち込みを見せている証左といえます。
もう1つ重大な歴史的事実を振り返っておく必要があります。都市の長期戦略を見誤ると取り返しのつかない事態を引き起こすことを忘れてはなりません。高度成長期に、1968年の「名古屋市将来計画・基本計画」で示した「都心地区」(栄・名駅含む)以外の「副都心地区(太閤、浄心、大曽根、今池、金山、桜山、堀田、熱田など)が、都市戦略の失敗により、活況を無くしていきました。当時、名古屋市周辺の市町村を大規模に合併させ、名古屋市の都市域拡大を前提としていくつかの商業地を「副都心」にさせる構想があったのです。事態はそのように進まず、失敗しました。多くの関係者の街づくりへの努力が実らず、単なる通過交通地点になったというのは言い過ぎでしょうか。都市のあるべき方向を冷静に見極めることがいかに重要であるのかが最大の教訓です。そして今回の「ビジネス拠点・交流拠点」形成です。街づくりはそこに住む住民の仕事と暮らし、何よりも命が関わっています。単なる願望ではない、責任を持った名古屋の進路を選び取る必要があります。先に名古屋市及び愛知県の計画が「ストロー現象を懸念する」と紹介した大きな問題がここにあります。名古屋市などの一部の繁栄と同時進行で空洞化が進むことの懸念です。各界の方々と共に大きな討論を巻き起こしていく必要があります。
(2)大規模開発の歴史の教訓
2005年「万博・空港」戦略とその後
この間の愛知県下の歴史の教訓をもう少し見てみます。例えば、2005年の「万博・空港」をめざした時の愛知県の自治体政策です。愛知県は、2005年に向けて長期にわたって「2大プロジェクト」に代表される公共事業に最大の軸足を置いて取組んできました。愛知県負担額は3,000億円近く(貸付金含む)になり、福祉・教育部門は大きな後退を招いてきました。民間法人企業所得は好調な反面、雇用者報酬等では大きな問題をはらんできました。それでは2005年を迎えた時に、県民にとってバラ色の時代を迎えたのでしょうか。当時の新総合計画『新政策指針』策定論議では、自動車産業の国際競争力強化に貢献することを前提に、従来の行政手法に限界があるとして「選択と集中」の政策展開を提示したのです。高齢化社会の進展と、他方で愛知における生産拠点の海外展開が急速に進むなかで、地域経済の疲弊と民生軽視の公共サービスが続きました。「選択と集中」による福祉・教育部門の撤退・職員削減ではなく、高規格道路整備を中心とする公共事業の転換こそが求められていたのです。
「万博・空港」を含む愛知県の戦後一貫した産業政策の核心部分は、屈指の自動車産業集積地を形成してくることでした。それが「元気な愛知」と称賛されてきました。しかし、2008年経済危機、2011年東日本大震災は、それまでの産業構造の脆弱性を露呈させ、産業と自治体財政を危機に陥れました。これまでに愛知県は工業用地開発を積極的に進めてきましたが、その反面で公共の名により自然環境の激変と環境破壊を進めてきました。1960年頃からの約40年間で、ナゴヤドーム2000個相当分の工業用地(関連用地含む)を開発してきたのです。
20世紀型開発とは何だったのか
高度成長期の開発の象徴としての田中角栄『日本列島改造論』(1972年)は何だったのでしょうか。元首相は、「新幹線と高速自動車道の建設、通信ネットワーク形成をテコに、都市と農村、格差を必ずなくす」と主張しました。実態は、規模の巨大さ、地域産業を育てない外来型開発、環境破壊、没個性化の開発、しかも大型公共投資中心の経済成長至上主義ではなかったのではないでしょうか。オイルショック、物価高騰等で主張は挫折しましたが、その在りようは後に継承されていきました。最大の問題は、人間がそれぞれの地域社会で営んできた総体としての文化の個性をなくしてしまったことです。
これと比較して、現下の開発はどう見ればよいのでしようか。JRが単独で9兆円もの建設費用を全額負担するという。「なぜ民間の1企業が」との疑念があるようですが、筆者にはそうは思えません。財務省のHPでは2014年度末の公債残高は約780兆円(税収の約16年分)であり、将来世代に大きな負担を残すと喧伝しています。しかも1990年代後半に財政健全化を進めた先進国に比べ最悪になっていると述べます。財政健全化の当否は別にして、民間に事実上の公共投資を進めさせるところに今日の事態の深刻さが表れていると言えましょう。今日では表向き公的資金の活用は困難であり、民間資金を動員させています。この点はかつての時代と様相は異なります。しかし、それを除けば開発の巨大さ、環境破壊に留意しないことは共通で、同根の思想であるといえます。山岳地帯を貫くトンネルは難工事が予想され、建設費が膨らむことは避けられそうにありません。アベノミクスで長期金利も上がると見込まれています(日経電子版、2015年10月4日)。
開発には、こうした動きに抗して新しい時代を築いた歴史も刻まれています。五十嵐敬喜・小川明雄『「都市再生」を問う―建築無制限時代の到来』(2003)には、「規制緩和から規制強化へ」の項で、「高度成長時代は、市民からみれば、自動車事故、渋滞と排気ガス公害、地価高騰、建築紛争激化、日常生活が危機に」陥れられた。そうした中で、「宅地開発指導要綱」や「町づくり条例など」を市民の側が作っていったことが紹介されています。こうしたことに確信を持ち、広範な国民共同の力で取り組むことがいま求められています。