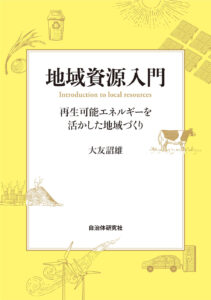地方分権「改革」とは一体何であったのか。その検証を通して、憲法・地方自治法施行70年目を迎える地方自治の現状と憲法に基づく地方自治の実現に向けた今後の展望を考えてみます。
はじめに
2017年は、日本国憲法の施行、そして地方自治法の制定・施行から70年目の年に当たります。憲法は、国民主権、基本的人権の保障、平和主義と並んで、「地方自治」にひとつの独立した章(第8章)を与え、団体自治と住民自治からなる「地方自治の本旨」(92条)を保障するとともに、長と議員の直接公選(93条)、自治体の立法権(条例制定権)・財政権・行政権の保障(94条)を定めることによって、天皇制国家のもとで国の強い中央集権的支配に服していた戦前の地方団体の地位を、真の自治体へと飛躍的に向上させることになりました。地方自治法は、この憲法第8章を具体化するために定められた法律であり、地方自治に関する基本法としての性格をもつものにほかなりません。
しかし、いまわたしたちは、憲法第8章に基づく地方自治が本来の姿で実現され定着してきたことを素直に喜びながら、憲法・地方自治法施行70年を迎えることができる状況にあるでしょうか。答えは、否といわざるをえません。地方自治の定着と発展どころか、憲法と地方自治をめぐる現在の状況は、現政権のもとでかなり危機的な様相を呈しつつあるといっても過言ではないでしょう。
憲法による地方自治の保障にもかかわらず、なぜこのような本来の姿と相いれない〝地方自治破壊〟とでもいうべき状況が生み出されてきたのでしょうか。そして、現在の時点に立って、憲法に基づく真の地方自治を実現していく展望をどのようにして切り拓いていくことができるのでしょうか。本稿では、1990年代に大々的に展開され今日にまで引き継がれてきた地方分権「改革」(以下「」は省略します)の検証を通して、このことを考えてみたいと思います。
地方分権改革とは
ここでいう地方分権改革とは、1995年の地方分権推進法とそれに基づく地方分権推進委員会の設置によって開始され、同委員会の5次にわたる勧告を経て、1999年の地方自治法の改正を含む地方分権一括法の制定へと結実することとなった一連の改革のことを指しています。この改革の結果、戦後の地方自治の確立を妨げてきた大きな要因のひとつであった機関委任事務制度が廃止され、自治体の事務は、自治事務と法定受託事務とに分けられ、そのいずれもが自治体の事務として条例制定の対象とされることになりました。また、国の自治体に対する関与の仕組みも明確化され、自治体の自主性・自立性に配慮して、国の関与は目的達成のために必要最小限度にとどめなければならないとの原則が定められました。さらに、国と地方の間の紛争を処理するための機関として国・地方係争処理委員会が設けられ、国の関与に対する不服申立てと裁判の仕組みが整えられることとなりました。
この分権改革は、21世紀に入って、分権改革の受け皿づくりの名のもとで進められた「平成の大合併」、国庫補助金の削減と国から地方への税源移譲、地方財源の大幅削減を内容とする「三位一体改革」へと引き継がれ、さらに、2007年に設置された地方分権改革推進委員会の勧告に基づいて進められた「義務付け・枠付けの見直し」をはじめとする一連の分権改革・地域主権改革へと継承されることになります。このようにして今日まで続けられてきた一連の分権改革のうち、地方分権一括法までの前段の分権改革を第1次分権改革、それ以降の分権改革を第2次分権改革ということもありますが、いずれにせよ、これらの分権改革は、政権のいかんを問わず、この間の大きな政治課題のひとつを形成してきたということができます。
新自由主義改革と一体の地方分権改革
機関委任事務の廃止に象徴されるように、分権改革によって、法制度・法形式のうえで自治体の自主性が高められたことは否定できません。では、それによって、実際に国と地方の対等な関係が築きあげられたかというと、答えは否です。それどころか、政府は、この間、集中改革プランの自治体への強要に象徴されるように、さまざまな分野で、多様な手法を使って、国が決めた政策に地方を従属させてきました。第1次分権改革以降の事態を冷静に見る限り、実態面では、国の地方に対する統制は分権改革以前よりも強化され、地方の国への従属が強められてきた、というのがわたしの率直な感想です。このことは、いかに形のうえで法制度を整えても、現実の政治・社会の場で国と地方の真の対等関係が確立されない限り、法制度上の分権化も絵に描いた餅になりかねないことを示しています。
鳴り物入りで展開されてきた分権改革にもかかわらず、なぜこのような結果を招くことになったのか。わたしは、その根本原因が、次の3点にあると思っています。
その第1は、分権改革が「官から民へ」の新自由主義改革と一体的に進められてきたということです。地方分権推進委員会は、分権改革の開始の時点において、改革のキーワードとして「自己決定権─規制緩和と地方分権」を打ち出し、「国から地方へ」の分権改革と「官から民へ」の規制緩和との一体性を強調し、この2つの課題が並行して徹底して推進されたときに初めて明治維新、戦後改革に続く「第三の改革」が成就する、との認識を示しました。
周知のように、規制緩和は、民営化とともに、前世紀末葉以降急速に進められてきた財界本位の新自由主義改革の柱をなすものにほかなりません。すなわち、地方の自主性の拡大をめざす分権改革は、当初から規制緩和を柱とする新自由主義改革と一体の関係として位置づけられ、それと両立する限りでの分権改革であったということになります。そして、それを正当化するために持ち出されたのが、自治体の「自己決定権」という、それ自体としてはだれも否定することのできない崇高な理念であったということができます。
右に述べた地方分権改革の新自由主義的な性格は、21世紀に入って以降いっそう強められ、第2次分権改革の時点では、その進め方の点でも、その内容の点でも、財界本位の側面が前面に押し出されてくることになります。
国の役割強化、強権的国家機構づくりと一体の地方分権改革
その第2は、これまた今次分権改革のキーワードである「国と地方の役割分担」です。第1次分権改革の出発点となった第3次行革審(臨時行政改革推進審議会)の最終答申(1993年)は、「国は外交、安全保障を始め国の存立にかかわる課題に重点的に取り組む体制を築く一方、地域の問題は住民の選択と責任の下で地方自治体が主体的に取り組めるようにする必要がある」として、その後の改革を方向づけました。改正地方自治法1条の2第2項で、国は「国が本来果たすべき役割」を担い、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねる」ことを基本とする「国と地方の役割分担」が定められましたが、その基本には、右にあげた第3次行革審の考えがあることを見ておく必要があります。
すなわち、ここで描かれている分権改革とは、一方で国が外交、安全保障などに専念できるようにするための分権改革であり、他方では、福祉、教育など住民の生存権・社会権保障に関わる行政分野において、憲法で定められた国の役割を放棄・限定し、それを「住民の選択と責任」のもとで自治体に転嫁するための分権改革にほかなりません。これによって、外交・安全保障について国が自治体の意向を排して専権的に進めることができる体制を構築しようとした国の企図は、まさにいまの沖縄の事態に如実に示されています。
第3は、第2のこととも関連しますが、分権改革が、時期的にも内容的にも、国家機構の再編強化と一体的に進められたことです。すなわち、第1次分権改革が進められた時期は、中央省庁改革が進められた時期とほぼ重なっています。後者は、いわゆる政治主導・内閣主導を推進するために、内閣と内閣官房の権限を強化するとともに、内閣を補佐するための組織として内閣府を新設し、そのもとに経済財政諮問会議をはじめとする各種の会議体を設置して、労働者をはじめとする国民各層の声を排除しながら財界本位の政策を決定できる仕組みを作りあげました。現政権のもとでいま起こっている一連の事態(加計学園・森友学園問題、共謀罪法の強行など)は、まさにこうした中央省庁改革によって築かれた強権的国家体制のもとで生み出されたものにほかなりません。そして、地方分権改革は、この中央省庁改革と並行しながら、それと一体の関係のもとで進められてきたことを直視する必要があります。
地方分権改革の評価
地方自治の観点から見て、分権改革が一定の成果を残したこと自体は正当に評価する必要があります。また、そこに、国と地方の対等な関係の確立を求めて運動してきた自治体関係者や研究者の願いが反映されていることも否定できません。そして、こうした分権改革の成果は、今後、憲法第8章に基づく地方自治の確立と伸長をめざす運動に対して、一定の手がかりを与えることにもなるでしょう。
しかし、以上のことを踏まえたうえでもなお、地方分権改革は、その全過程を冷静に見る限り、一方では、1980年代に始まり1990年代以降本格的に展開されることとなる新自由主義改革の大波に飲み込まれるとともに、他方では、2大政党による「政権交代可能な政治システム」の実現をめざして行われた1990年代の「政治改革」(小選挙区制と政党助成制度)、そしてそれを支えるための「政治主導」体制の構築=内閣を頂点とする国家機構の再編強化の一環に組み込まれることとなった、と評価せざるをえません。結局、地方分権改革は、これら2つの大きな流れの枠内において推進され、それと両立する限りでの分権改革であったということになります。ここに、憲法に基づく真の地方自治の確立とは異なり、形のうえでの国の事務・権限の地方への移譲にとどまる文字通りの「分権」改革の限界があった、とわたしは考えています。
地方自治を支えるのは住民の力と運動
地方分権改革の時期よりも前の1960~1970年代に、地方自治の実現に向けた動きが全国に広がり、自治体の先進的な施策が国の政策をも変えていった時代がありました。この時期は、〝公害問題の激化や福祉の立ち遅れなどの社会問題の深刻化→住民運動・労働運動の生成・発展→革新自治体の誕生と全国への波及→革新自治体による先導的・先進的な施策の推進→保守自治体を含む全国の自治体への波及→国によるその受容〟といった地方自治発展のサイクルが見事に示された時代でした。戦後地方自治が最も輝かしい成果をあげた時代といってよいでしょう。
この時に地方自治の発展を支えたのは、何よりも住民の運動とそれに支えられた民主的政治勢力(革新自治体・革新政党など)であり、この点が、後の地方分権改革との決定的な違いであったということができます。すなわち、地方自治発展の最大のよりどころは、それを妨げようとする勢力(国・保守政党・財界など)に対抗して住民の福祉の実現をめざして展開される下からの運動にこそある、ということになります。この下からの運動には、住民運動、市民運動、労働運動、消費者運動など多様なものが含まれますが、ここでは、住民全体の奉仕者たる自治体労働者が果たす独自の役割の重要性についても、あわせて指摘しておきたいと思います。
国政の民主的転換も視野に入れて
もうひとつ強調しておきたいことは、憲法に基づく地方自治の確立は、国政の転換=民主化と結びついて初めて真の意味で語りうるということです。日本国憲法は、国民主権の原理を宣言したうえで、国民の基本的人権の保障を国の責務と定めています。ここで国というのは、狭い意味の中央政府だけなく、地方自治体も含めた広い意味での国と考えられますので、憲法が定める基本的人権は、国(中央政府)と地方自治体の双方の場を通して実現されなければならないということ、言い換えると、日本国民は、憲法上、国政と地方政治の双方の場において二重の意味で基本的人権を保障されている、ということになります。そうすると、先に述べた生存権や社会権の分野でも、国民に対してそれを保障すべき国と自治体の双方の責任を明確にしたうえで、地方自治権の保障を前提とした両者の協力関係を確立していくことが必要になってきます。そして、それを実現するためには、国民生活を犠牲にして財界本位の新自由主義政策にまい進する現在の国政のあり方を根本的に改め、憲法に基づく国民の生存権・社会権保障を第一義的課題とする国民本位の民主的国政への転換を図っていくことが、不可欠の課題となってきます。
平和主義の実現をも展望して
国政との関係でさらに指摘しておかなければならないことは、沖縄の現状が示すように、右のような国と自治体の関係を確立する課題は、憲法が定めるもうひとつの基本原理である平和主義を実現していく課題と不可分の関係にあるということです。いま沖縄では、辺野古基地建設反対、普天間基地を含む米軍基地の廃止・縮小というオール沖縄の願いと、沖縄県民の意向を排除して日米軍事同盟の再編強化に突き進む現政権の強権的姿勢とが鋭く対立しています。こうしたなかで、オール沖縄の願いを実現するためには、政府に対して沖縄の自治権を尊重させるという課題にとどまらず、究極的には、日米安保条約の廃棄による沖縄からの米軍基地の撤去という課題の実現が不可欠となることは明らかです。そして、この問題はいうまでもなく沖縄だけにとどまるものではなく、憲法に基づく地方自治確立の課題と日米安保体制の廃棄=平和主義の実現の課題は、日本国民全体にとって一体的に追求されなければならない共通の課題であることを最後に確認しておきたいと思います。
* 本稿の内容については、晴山一穂『現代国家と行政法学の課題』(日本評論社、2012年)の第5章「地方分権改革と国家行政機構の再編」、第6章「地域主権改革と国家・自治体の役割」でより詳しく論じていますので、あわせてご参照願えれば幸いです。