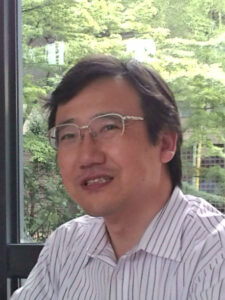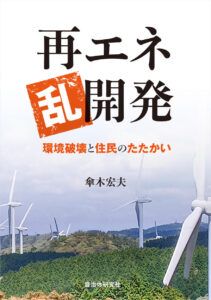「ふるさと納税」は「ふるさと」への「納税」ではない
「ふるさと納税」は、納税者の「ふるさと」の自治体への「納税」ではありません。まず自治体への納税ではなく、「寄附」です。また、納税者にとっての「ふるさと」の自治体への寄附である必要はなく、 東京都以外のどの自治体に対する「寄附」にも適応される制度です。
「ふるさと納税制度」に係る控除額の仕組みは以下のとおりです。個人が都道府県・市区町村に対して「寄附」を行うと、寄付額のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額控除するというものです(なお、東京都は「ふるさと納税制度」に参加していません)。具体的な控除のイメージは図1のとおりであり、要は住民税所得割額の2割を上限として、[寄付額-2000円]の全額が税額控除されることになります。住民税所得割額が多額となる高額納税者ほど限度額も高くなります。たとえば住民税所得割額が50万円であれば、その2割である10万円が限度額となり、10万円をある自治体に寄附し、その自治体からの返礼品の価値が3万円であった場合、2万8000円(3万円-2000円)分の価値を得ることになります。また、住民税所得割額が200万円であれば、その2割である40万円が限度額となり、40万円をある自治体に寄附し、その自治体からの返礼品の価値が12万円であった場合、11万8000円(12万円-2000円)分の価値を得ることになります。別の見方をすれば、その分だけ実質的な節税を図れたことになります。
以上のように、「ふるさと納税制度」は、納税者が魅力的な返礼品を提供する自治体に寄附を行うことへの強力なインセンティブを提供しています。
つまり、「ふるさと納税制度」は2000円の「手数料」だけで、その数倍、あるいは数十倍の価値のある「お得」な返礼品がもらえるという制度であり、納税者の多くは寄附受け入れ自治体が提供する「お得」な返礼品を得ることが動機となって制度を利用しているのであって、本来の「寄附」とはほど遠いものです。
これまでも寄附税制はありましたが、それは「ふるさと納税制度」と決定的な違いがあります。認定NPO法人等に適用される寄附税制においては、納税者が認定NPO等に寄附を行うと、その寄附額について所得税において所得控除を受けられる仕組みとなっています。それゆえ、節税効果は寄附額の一部に過ぎません。寄附とは本来、対価を要求しないものです。たとえ寄附先からいくらかの返礼品を受け取ったとしてもそれが寄附額を超えることはありえません。寄附を行う者が金銭的な負担をするのは寄附の趣旨からいって当然の姿です。しかし、「ふるさと納税」は違います。寄附を行う者が負担するどころか大幅に得する制度なのです。この点からみると、 「ふるさと納税」はもはや寄附ですらありません。
自治体はなぜ「ふるさと納税」に取り組むのか
「ふるさと納税」はそれを得る自治体にとっては「寄附金」ですが、納税者からみると居住自治体に納めるべき住民税納税額の一部が控除(減額)され、その分が「寄附」として「ふるさと納税」を受ける自治体の財源になります。つまり、実質的に納税額の一部が居住自治体から寄附金受け入れ自治体に移転されることになります。その側面を「ふるさと納税」という名称が表わしているのです。多くの自治体が「ふるさと納税」寄附を得ようとすることに対して、「ふるさと納税」の「寄附」を財源とした地域振興や返礼品による産業振興への肯定的な見解もあります。その一方で、 市場を歪め「下駄をはかせた」返礼品ビジネスが地域経済の活性化につながるかについての根本的な疑問も出されています。
「ふるさと納税制度」は返礼品を手段とした熾烈な税源の奪い合いを引き起こします。主に税収を奪われているのは本誌11月号の世田谷区の事例をみてわかるように、大都市圏の自治体です。近年では、税収を奪われてきた大都市圏の自治体も積極的に「ふるさと納税」に取り組んでおり、それによって少しでも税源の喪失をカバーしようとしています。たとえば、2022年度の「ふるさと納税」寄附受入額の7位に京都市が、14位に名古屋市が入っています。
政府はなぜ「ふるさと納税制度」を導入し、拡大させたのか
ふるさと納税制度は2008年度地方税制改正によって創設されましたが、2015年度税制改正により、住民税所得割の特別控除の上限が1割から2割に引き上げられるとともに、確定申告なしに控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。この特例制度が適用される場合、所得税控除相当額を含め翌年度の住民税から控除されます。ワンストップサービスはマイナンバー、マイナポータルを活用した簡素化までの間の特例的な仕組みとして導入されるとの説明がなされており、この特例が適用される納税者は「ふるさと納税額(受入れ寄付額)」の3割を超えています(2022年度、総務省調査による)。
筆者は安倍政権下での地方財政改革を集権的地方財政改革と特徴付けしました。集権的地方財政改革は①競争主義改革(マイナスサムゲーム下での自治体の「生き残り競争」を促進)、②自治体空洞化改革(行政の「標準化」、「アウトソーシング化」、「産業化」を促進)、③圏域行政化改革(拠点化、広域化、圏域単位の行政を促進)の3つの内容からなっており、そのうちの競争主義改革の主な手段として 「ふるさと納税制度」が位置づけられていると考えられます。自治体は、財政難や地方交付税の不足を嘆くのでなく、「ふるさと納税」寄附を頑張って得ることによって地域振興を図れと追い立てられます。こうしたマインドを促すことで、国にとっては地方一般財源保障の貧困さへの批判をかわす効果もあるでしょう。他方では「負け組」には「あきらめのマインド」を促し、自治体空洞化や圏域行政化へと誘導し、地方行財政の合理化を促進するねらいがあります。
「ふるさと納税制度」の本質的問題点
「ふるさと納税制度」の問題点は、これまで財政学者や税法学者などから批判されており、筆者も以前から 「ふるさと納税制度」の問題点を指摘してきました。「ふるさと納税制度」の本質的な問題点として、以下があります。
第一に、税の原理原則に反していることです。税は寄附とは異なり法律や条例にもとづいて強制力をもって賦課・徴収されるものであり、住民が自由意志で納税先を選択できるというのは税の原理原則に反します。 住民税は居住自治体のサービスに対して税負担するという応益課税の原則にのっとったものですが、納税者の判断で非居住地自治体を選択し、「納税」するというのでは、応益原則に反しており、納税者間の不公平をもたらします。
第二に、地方自治を毀損するものです。納税者の自由意思によって「納税先自治体」を「選択」できるというのは自治体の徴税権を侵害するものです。税収を奪われる都市自治体は財源の減少によって行政サービスやインフラ整備等にも影響してきます。
第三に、高額納税者への優遇税制(2000円の負担で高額な返礼品)による不公平です。高額納税者ほど、限度額が高く、 2000円の負担だけで「濡れ手に粟」の返礼品を獲得できるのです。
第四に、過度な返礼品競争による「税の奪い合い」が自治体行政に歪みをもたらし、自治体間格差を拡大するとともに、都市と農山漁村の自治体間の対立と分断を生むことです。
第五に、高額な返礼品や経費により寄附税制としての効率性が確保されないことです。総務省によれば2022年度の実績では寄附額の約47%が返礼品や事務経費等に費やされています。さらにそれ以外にも隠れた経費があると指摘されています。国・地方をつうじた全体としてみれば、 貴重な税収の5割近くが返礼品、送料、ポータルサイト委託費、広告費、事務委託費等に消えているのです。
規制強化策では「ふるさと納税制度」の本質的問題は解消しない
2019年度に総務省は「ふるさと納税新制度」を導入しました。新制度とは、これまで全ての自治体に認めてきたふるさと納税制度を、総務省が指定した自治体にのみ適用するというものです。そのうえで、次の指定基準が設定されました。①返礼品は地場産品とする(製造・加工等による域内付加価値)、②返礼品の調達額は寄付額の3割以下、③返礼品を強調した宣伝広告はしない、④総経費は寄付額の5割以下。
また、2023年10月からふるさと納税にかかった自治体の経費の算定対象が拡大されています。しかし、返礼品の対象制限や経費の制限などの規制強化では上記で整理したような「ふるさと納税制度」の本質的問題点は全く解消されません。
「ふるさと納税制度」廃止への道
「ふるさと納税制度」が孕む本質的な問題点は小手先の修正で解消されるものではないことから、問題を解決するには制度そのものを廃止するほかありません。「ふるさと納税制度」が地方都市や町村の地域振興に「貢献」する側面をみて功罪を論じる向きもありますが、そのことによって 制度の本質的で重大な問題から目をそらすべきではありません。
税の原則に全く反し、さまざまな歪みや不公平をもたらしたふるさと納税制度は廃止すべきです。財政学者などからは認定NPO等への取り扱いに準じるように寄付税制に改正する方向が提案されています。
ただし、「ふるさと納税制度」によって、言わば「返礼品市場」が形成されており、地域の事業者によっては返礼品が売り上げに大きく貢献しているケースも多くなっていることを鑑みれば、 現実的には制度の廃止は段階的に進められる必要があるでしょう。 ただし、それは制度の廃止時期を明確にしたうえで進めなければなりません。返礼品による産業振興を図ってきた自治体は、「下駄を履かせ」なくとも売れる商品開発等を独自に支援することが求められるでしょう。
また、ふるさと納税制度の段階的廃止のプロセスにおいて地方交付税の拡充を同時に進めていくことが求められます。 非効率な制度によって「税の奪い合い」を煽るのではなく、全国の自治体へのナショナルスタンダードな一般財源保障を拡充することが制度改革の基本的方向になるのです。