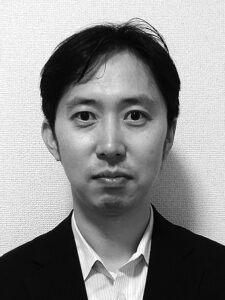日本はすでに24基の商用原発廃炉が決まり世界有数の廃炉原発立地国。廃炉中にも続く使用済燃料リスクに対して立地地域が前もって議論すべき論点を探る。
現在実施中あるいは検討中の廃炉計画の多くは、廃炉中の原発敷地内で使用済燃料貯蔵を続けることを前提としています。廃炉中の使用済燃料関連リスクを地域社会の側からどう監視し、どんな対策を打つべきか。本稿では米国の廃炉先行地域を参考に、日本で議論すべき論点を提示します。
廃炉プロセスと地域からの要チェックポイント
多くの場合、廃炉期間中にも敷地内で「使用済燃料」を長期(場合によっては数十年間)貯蔵し続けることになります。廃炉は住民の安全や周辺環境に影響を与える長期事業であり、地域社会からの監視が必要です。
では、「30年~40年」ともいわれる廃炉プロセスの、「何」に対して関心を持ち、チェックすればよいのでしょうか。図に通常の廃炉プロセス(①~⑥段階に区分)を示しました。
まず廃炉作業を開始する前に、事業者は「廃炉計画(廃止措置計画)」を国の原子力規制委員会に提出し、認可を受ける必要があります(①)。原子力規制委員会は事業者が安全上の規則を守っているかをチェックしますが、廃炉による地域社会への影響を考慮するわけではありません。放っておけば、「廃炉完了に何年かかるか」「使用済燃料はどうやって保管するのか」といった地域の将来にかかわる問題も、地域住民抜きで決められてしまいます。本来は、廃炉計画の審査段階から地域住民が議論に参加できるよう、前もって条例や協定で定める必要があります。
原発施設解体の前に「使用済燃料の搬出」が行われます(②)。しかし「搬出」といっても、このタイミングで「立地自治体の外」に搬出されるわけではありません。通常、廃炉決定した原発では、原子炉から抜き出された使用済燃料はまず敷地内の燃料プールで冷却されます。このプールでの保管が長期間続くこともあることに注意が必要です。冷却済みの燃料をプールから敷地内の「乾式貯蔵施設」(後述)に移し、廃炉原発での保管がさらに長期化する例も増えています。
そのため、原発立地地域がすぐに使用済燃料から解放されるわけではないのです。使用済燃料保管が続く限り、燃料損傷などの災害リスクは残ります。燃料貯蔵施設の安全性をチェックするとともに、事故を想定した防災上の施策も続けなければなりません。
施設解体のプロセス(図③~⑥)では、周辺地域への環境汚染対策が一つの論点となります。除染・解体作業中に生じる粉じんや汚染水が周辺地域・水域に流出することを防ぐ対策が必要になります。
2021年現在、日本で廃炉が完了した商用原発はまだありません。図⑥の施設解体を経て「廃炉完了」となります。しかし、現在実施・検討中の廃炉計画では「廃炉完了時点で原発跡地がどのような状態になっているのか」曖昧な点が多く残ります。例えば、東海発電所(茨城県東海村─廃炉計画実施中)の廃炉では、隣接地に低レベル放射性廃棄物処分場を作る計画が進められています。
米国でもいまだに使用済燃料最終処分場が決まらず、原発跡地に「使用済燃料貯蔵施設」が残され、負の遺産を抱え続ける自治体が増えています。廃炉後の敷地が「廃棄物処分場」や「使用済燃料貯蔵施設」になってしまう、というシナリオは防がねばなりません。そのためにも、地域住民が廃炉計画の段階から目を光らせ、ルール作りを主導する必要があります。
廃炉中の地域防災継続を保証する制度整備を
すでに述べた通り、多くの場合、廃炉決定後も敷地内のプールで使用済燃料の保管が続きます。使用済燃料貯蔵中のプールで事故が起きれば、原子炉内の事故の場合よりも周辺環境への影響は大きいとされます。廃炉決定後、この「プール内保管」が20年以上続くこともあるのです(福島第二原発廃炉計画等)。この意味で廃炉中の原発は、地域住民にとって依然として「災害リスク施設」です。廃炉中にどのような安全対策が行われるのか、緊急事態用の施設や機能は十分に維持されるのか、注視する必要があります。
福島第一原発事故後、日本では原発周辺地域(おおむね半径30キロメートル圏)では避難計画の策定が義務付けられています。放射線状況を把握するための緊急時モニタリングセンターや、内部被ばくを防ぐための安定ヨウ素剤配布準備など、周辺自治体にはソフト・ハード面での原子力防災体制が求められるようになりました。原発の運転事業者にも緊急時に備えた非常用電源、事故対応施設、通信インフラの整備や、緊急時対応要員の配置・訓練などが求められます。
廃炉が決定した後、これら地域住民を守るための防災体制はどうなるのでしょうか。商用原発廃炉で20年以上の歴史を持つ米国では、「廃炉中は事故リスクが下がる」として、周辺地域の防災計画を縮小する動きがあります。
米国では原発周辺10マイル(約16キロメートル)圏に「緊急時計画ゾーン(通称EPZ)」が設定されています。EPZ内の地域と原発事業者には、原発事故に備えた避難・屋内退避計画策定、被ばく防護のための安定ヨウ素剤配布、地産食料品摂取規制策等が求められます。これは広域での住民避難に至ったスリーマイル島原発事故(1979年3月)の教訓をもとに作られた地域防災制度です。
しかし近年米国では、廃炉決定後の原発周辺地域で、このEPZを「消してしまう」動きがあります。2014年末に閉鎖されたバーモントヤンキー原発(バーモント州ウィンダム郡)の周辺地域では、2016年4月にEPZが撤廃されました。これにより緊急時対策対象エリアは原発敷地内だけとなり、それに伴い、原発事業者Entergy社は周辺地域に対する「緊急時対策費用」支払いも免除されました。原発閉鎖から1年半も経たないうちに、大幅な緊急時対策の縮小が認められたのです。
米国では廃炉決定した原子炉から使用済燃料を貯蔵プールに移した後、事業者が原子力規制委員会(NRC)に緊急時計画要件の免除を申請することができます。NRCの規則は「廃炉中は原発運転中に比べて事故リスクが小さい」という考え方に立っています。バーモントヤンキー周辺地域のEPZ撤廃も、このNRCへの免除申請を経て認められました。このような「廃炉決定後の地域防災削減」は米国の他の立地地域でも繰り返されています。例えばピルグリム原発(マサチューセッツ州)では原発閉鎖(2019年5月)から約半年後(同年11月)に周辺地域のEPZ撤廃が認められています。EPZを撤廃された地域では、防災担当職員の人件費や避難訓練のための予算が削減され、廃炉期間中に十分な防災体制を維持できなくなることが懸念されています。
米国で起きている地域防災縮小を「対岸の火事」として眺めていてよいのでしょうか。日本でも今後、「廃炉の進行」を理由に、周辺地域を守る防災体制を縮小する動きがあり得ます。
資源エネルギー庁は、廃炉が進むにつれて事故の危険も減少するとの考えに立ち、「今後は、安全を第一としつつも、廃炉の各プロセスにおけるリスクに応じた安全規制を検討することも必要になると考えられます」と述べています(「原子力発電所の『廃炉』、決まったらどんなことをするの?」2019年3月15日)。今後、廃炉中の原発に対しては、従来の安全規則が変更される可能性があるのです。
そもそも「廃炉」は、安全対策用設備の解体・撤去を含む工程です。免震重要棟や非常用冷却系統など事故対応や防災のための設備もやがて解体されることになります。廃炉期間中、事業者が安全対策上必要な設備や機能を十分に維持するのか、注視が必要になります。
数十年続く廃炉期間中、周辺自治体が緊急時モニタリングセンターや避難計画などの防災体制をいつまで、どのように維持できるのかという課題もあります。これらの問題は財源確保も含め、あらかじめ議論しておく必要があるでしょう。廃炉中も事業者に十分な安全対策の継続を義務付け、地域防災継続のため国による予算措置を義務付ける制度が必要です。
「乾式貯蔵施設」の条件設定を住民主導で
米国などの廃炉先行地域では、冷却済みの使用済燃料をプールから取り出した後、敷地内に建設した「乾式貯蔵施設」で貯蔵を続ける方式が増えています。日本でも浜岡原発(静岡県)、伊方原発(愛媛県)など、一部廃炉決定した原発で乾式貯蔵施設増設計画が出されています。全基廃炉決定した福島第二原発でも敷地内乾式貯蔵施設の建設を検討中です。
しかし世界では、この「乾式貯蔵施設」が実質上の長期貯蔵施設となってしまう事例が増えています。その場合、「乾式貯蔵施設」の長期的な安全性が、地域住民にとっての懸念事項となります。
リスクの高いプール貯蔵長期化を避けるために、中間段階として「乾式貯蔵施設」を建設する選択肢を否定することはできません。それでも、日本では多くの原発が地震・津波リスク地域に位置しており、「乾式貯蔵施設」の新・増設の決定には慎重な議論が必要です。
「乾式貯蔵施設」建設計画に際しては、施設の耐震性・津波耐性や、環境汚染防止対策などを多面的に評価し、地域住民が意思決定に参加できるようにすべきです。一度建設を認めたとしても、そこで議論が終わりではありません。「貯蔵期間がどのくらい続くのか」「施設の保守管理はどうするのか」など、事業者に情報公開や追加対策を義務付ける仕組みが必要です。
しかし日本では、廃炉決定原発での「乾式貯蔵施設」建設・運用について、住民参画の機会が十分に保証されているとはいえません。福島第二原発廃炉計画では、同原発の使用済燃料全体の約半数(4万8000体)を新設の乾式貯蔵施設に移す計画です。さらに、残りの使用済燃料の搬出先が見つからなければ、乾式貯蔵施設の増設もありえます。楽観的に想定し廃炉完了時(開始から44年後)までに搬出できると仮定しても、20~30年近い期間、この「乾式貯蔵施設」での使用済燃料保管が続くのです。
しかし、この「乾式貯蔵施設」が「どのような施設」で「どのように運用・点検するのか」、その詳細は住民に説明されていません。「乾式貯蔵施設」を認可する権限を持つのは原子力規制委員会であり、自治体でも住民でもありません。地域の将来に負の影響を与えうる計画であるにもかかわらず、放っておけば、住民の目の届かない場で決められてしまうのです。
前出ピルグリム原発が立地するマサチューセッツ州では、住民代表や州政府職員から成る「廃炉市民助言パネル」が、独立専門家を招いて乾式貯蔵施設の安全性や経年劣化リスクなどを評価しています。この市民助言パネルは、原子力規制委員会や廃炉事業者に乾式貯蔵施設に対するテロ対策や独立安全審査などの追加対策を求めています。
カリフォルニア州政府機関である「カリフォルニア沿岸委員会」は、廃炉中のサン・オノフレ原発で建設される「乾式貯蔵施設」に「15年」という運用期限をつけています。同委員会は15年経過した時点での「乾式貯蔵施設」再審査を義務づけ、その時点での海面上昇や施設の経年劣化などを考慮して「施設の移動・撤去」「追加の安全対策」などを求めることができます。
これら米国の廃炉先行地域の取り組みを参考に、日本でも廃炉中の「乾式貯蔵」の条件を住民主体で決めていく必要があるでしょう。