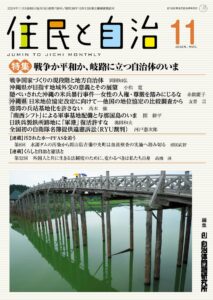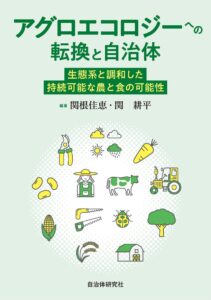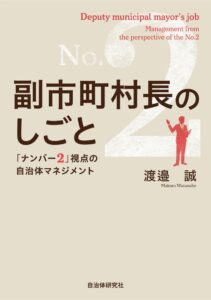論文・記事
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

自治体問題研究所/(株)自治体研究社
〒162-8512 東京都新宿区矢来町123 矢来ビル4階
電話: 03-3235-5941 / FAX: 03-3235-5933 /
E-mail info@jichiken.jp
© 2008-2024自治体問題研究所/(株)自治体研究社
© トップページ画像撮影:大坂 健(『住民と自治』から)